
公正証書の作成に関する行政書士費用は、原案作成報酬、代理人・証人の出頭日当が含まれています。
※公正証書の作成にかかる費用(行政書士報酬や公証人手数料などの実費)は、定める項目や取り決める金額・評価額により異なります。

公正証書とは? > 公正証書作成にかかる費用

公正証書の作成に関する行政書士費用は、原案作成報酬、代理人・証人の出頭日当が含まれています。
※公正証書の作成にかかる費用(行政書士報酬や公証人手数料などの実費)は、定める項目や取り決める金額・評価額により異なります。
| 公正証書の種類 | 行政書士報酬 |
| 債務弁済契約公正証書 | 55,000円 |
|---|---|
| 離婚給付契約公正証書 | 55,000円 ~77,000円 |
| 遺言公正証書 | 77,000円 ~99,000円 |
| 金銭消費貸借契約公正証書 | 55,000円 ~77,000円 |
| 売買契約公正証書 | 77,000円~99,000円 |
| 尊厳死宣言公正証書 | 77,000円 ~99,000円 |
| 任意後見契約公正証書 | 55,000円 ~77,000円 |
| 事実実験公正証書 | 77,000円 ~99,000円 |
| 上記以外 | 個別にご相談下さい。 |
| 出頭場所 | 行政書士報酬 |
| 弊所指定(東京23区) | 11,000円/1名 |
|---|---|
| 依頼者指定(東京23区) | 11,000円/1名+交通費実費 |
| 依頼者指定(東京都下・23区外) | 22,000円 ~33,000円+交通費実費/1名 |
| 依頼者指定(東京以外) | 33,000円 ~110,000円+交通費実費/1名 |
文面作成済で公証人チェック済みの場合には作成報酬は発生しませんが文面内容確認費用のみいただきます。
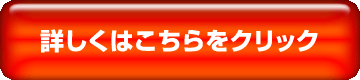
文面に定める金額や財産の価値評価額により、所定の公証人手数料がかかります。
金銭消費貸借契約、土地の賃貸借契約、売買契約、等の公正証書においては、印紙税法に定める、所定の印紙代がかります。
印紙は原本のみに添付となりますので、通常の契約書であれば、当事者2名であれば原本2部とも印紙の貼付が必要ですが、公正証書の場合には、原本が公証役場に保管される1通のみで足ります。
なお、離婚や遺言、任意後見、などの公正証書については、印紙代はかかりません。
| 金銭消費貸借契約における印紙税額 | |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え 50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え 100万円以下 | 1千円 |
| 100万円を超え 500万円以下 | 2千円 |
| 500万円を超え 1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円を超え 5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え 5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え 10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え 50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を 超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の 記載が無いもの | 200円 |
【例1】債務弁済契約における、100万超え200万以内で一般的な条件を定める場合の料金例
| 1.行政書士報酬 ※ご依頼時に必要 | |
| 文案作成報酬 | 33,000円 |
|---|---|
| 代理人日当 | 22,000円/2名分 |
| 2.実費(法定費用) ※作成前日までに必要 | |
| 公証人手数料 | 7,000円 |
| 正本・謄本代 | 6,000円 |
| 送達手数料 | 3,000円 |
| 収入印紙代 | 2,000円 |
| 合計 | 73,000円(税込) |
|---|
【例2】離婚給付契約における、子ども1名の養育費と不動産の財産分与を定めた場合の料金例。
| 1.行政書士報酬 ※ご依頼時に必要 | |
| 文案作成報酬 | 55,000円 |
|---|---|
| 代理人日当 | 22,000円/2名分 |
| 2.実費(法定費用) ※作成前日までに必要 | |
| 公証人手数料 | 17,000円(養育費 月5万1名) |
| 公証人手数料 | 23,000円(財産分与 不動産評価1000万~3000万) |
| 正本・謄本代 | 7,500円 |
| 送達手数料 | 3,000円 |
| 収入印紙代 | 0円 |
| 合計 | 127,500円(税込) |
|---|
作成に係る費用は、誰が(どちらが)支払うものなのでしょうか?
遺言書や尊厳死宣言など、単独の法律行為に関しては、通常、その公正証書の作成を求める人が費用を負担することになります。
契約に関する公正証書や契約書そのものの作成にかかる費用については、結論から言えば、特に誰が(どちらが)支払っても構いません。
事案により異なりますが、一般には、その公正証書や契約書の作成によって恩恵や利益を得る側が負担することが多いと思います。
例えば、当事者間の対等な契約においては、公正証書の作成にかかる費用を折半とする場合もありますし、当事者の一方が、今後のトラブル予防のため、弁護士や行政書士などの専門家に適切な契約書の作成を依頼して、作成費用を自分で支払う、という場合もあります。
また、事件や事故に関する示談契約においては、債務者(加害者)が作成にかかる費用を全額負担することで、債権者(被害者)に、刑事告訴しない・減額に応じる等の条件に合意してもらう、という場合も多くあります。
債務弁済契約においても、債務者が費用を全額負担することで、債権者が分割払いに応じる、等の条件で合意する場合があります。
離婚における養育費の定めなどについては、支払いを受ける債権者が、将来の安全のために、自己が作成費用を負担することを条件に公正証書での作成に同意承諾してもらう、という場合もあります。
契約時にかかる収入印紙代については、通常の契約は、当事者2名であれば契約書2部を作成して1部ずつ保管しますので、各々が自己保管分に貼付けすることが一般的ですが、公正証書においては、公証役場に保管される原本に貼付する1通分のみの足ります。